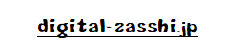パリコレクション(パリ・ファッションウィーク)
パリコレの概要/部門/主催団体紹介
| 主催団体 | フランス・オートクチュール・プレタポルテ連盟(Federation de la Haute Couture et de la Mode) |
|---|---|
| 主催団体の愛称 | サンディカ |
| 主催団体の略称 | FHCM |
| 正式名称(英語) | Paris Fashion Week |
| 3つの部門 | オートクチュール部門(注文服/仕立服) プレタポルテ部門(女性既製服) メンズ部門(男性既製服) |
| 開催時期(年各部門共に年2回) | オートクチュール部門=1月.7月 ウィメンズ・プレタポルテ部門=3月1日周辺/9月30日周辺 メンズ・プレタポルテ部門=1月/6月 |
| 参加価値 | ブランド的にもモデル的にも、参加歴をプロフィールに書き加えるだけで人生がいっぺんするほどの価値 |
オートクチュール部門しかなかった頃の初期のパリコレ
細かい起源は明らかになっておらず、あいまいな部分もあるものの、
もともとはパリの富裕層のみを対象とした
オートクチュール部門しか存在しなかった。
なお、オートクチュールの父など称される
イギリス出身のデザイナー、シャルル・フレデリック・ウォルトが
1800年代半ばに顧客のもとにモデル(マヌカン)と共に訪れ、
モデルに作品を着せて顧客に作品を見せていったのが、ランウェイショーの起源とされる。
その後、パリでは顧客の元を訪れてのショーではなく、
店のフロアに上顧客やジャーナリストを呼んで行う、
小さなオートクチュールショーが一般化。
日本では第二次世界大戦前後から
「パリコレクション」という文化が明確に伝わるようになり、
1950年代に入ってピエール・カルダンなどのトップデザイナーが
来日してショーを開催したり専門学校における特別講習を行う中で、
日本におけるパリコレに対する価値はどんどん高まっていた。
この時点ではまだ日本のブランドの参加はなかったが、
第二次世界大戦後に有名デザイナーが来日ショーを開催するケースが増える中、
ピエール・カルダンからのオファーを受けた松本弘子や
ルイ・フェローからのオファーを受けた松田和子といったモデルが
1960年前後にパリコレのオートクチュールショーにデビューを果たす。
つまり、1960年代からパリコレで活躍していたのは
日本人デザイナーではなく、日本人モデル。
1970年代に入ってプレタポルテ部門ができる
1960年代に入るとココ・シャネルなどオートクチュールにこだわるデザイナーとは別に、
- ピエール・カルダン
- イヴ・サンローラン、
- ギャビー・アギョン(Chloe創業者)
- ソニア・リキエル
など、富裕層だけが買えるオートクチュールだけでなく、
幅広い所得層の女性が買えるプレタポルテ(既製服)事業に力を入れる
若い世代のデザイナーが次々に登場。
1970年代に入ると高田賢三(1965年渡仏)のKENZOなど
最初からオートクチュール部門をもたないプレタポルテ専業ブランドが
急激に増えていき、そんな中で
KENZOなどの新人ブランドが開催したプレタポルテ系の合同ショーがきっかけとなり、
オートクチュール部門に加えてプレタポルテ部門が創設される。
また、高田賢三らが開催した合同ショーの存在により、
短い期間の中でたくさんのデザイナーが集中的にショーを開催する
「ファッション・ウイーク」という概念が徐々に出来上がっていく。
(短い期間の間にショーを集中開催するのは、
世界中からやってくるメディアが低コストでパリに滞在できるようにし、
それにより、よりたくさんのメディアを呼び寄せようという意図もあり)
日本的には1970年代前半に
- KENZO(高田賢三)
- ISSEY MIYAKE(三宅一生)
- KANSAI YAMAMOTO(やまもと寛斎)
といったブランド/デザイナーがプレタポルテ部門に参加しはじめて、
一気に世界的デザイナーへと昇りつめた。
また、それら日本人デザイナーのショーの主役として
山口小夜子というモデルが毎シーズン起用され、
彼女もまた日本人スーパーモデルの先駆けとなった。
1970年代半ばから後半にかけてもさらに
コシノジュンコやユキトリイがプレタポルテ部門にデビュー。
なお、1970年代半ばの時点で
オートクチュール部門に参加する日本ブランドは存在しなかったが、
NYでのビジネスを成功させた森英恵が
1977年にオートクチュール組合への加盟を許可され、
彼女はプレタポルテではなくオートクチュール部門デビューを果たしている。
1980年代以降はプレタポルテ部門が完全に主役
パリコレにプレタポルテ部門が創設されると
ごくわずかな人達を対象とするオートクチュール部門に対する
注目度は一気に薄れて世界中のメディアの注目は
プレタポルテ部門へと注がれるようになり、
あっという間にプレタポルテはオートクチュールを凌駕。
1980年代に入るとプレタポルテ部門の
- ショー会場の規模
- 呼び寄せるマスコミの数
- 呼びよせるセレブ(各国のタレントなど)の数
はどんどん高くなっていき、巨大な会場で世界中のトップモデルを集めて
大規模なショーを行うブランドが増加。
その流れの中、「自分達も負けまい」という意地の張り合いの中で
プレタポルテのショーの開催規模は1980年代に大きく拡大。
それにより、パリコレ(パリ・ファッションウイーク)というものの存在は
世界各地にてより高く扱われるようになった。
1980年代の日本との関係としては、
1981年に
- 川久保玲のコムデギャルソン
- 山本耀司のヨウジヤマモト
がプレタポルテ部門にデビューしたのを皮切りに、
1982年にはイトキンの支援を受けたコシノヒロコもデビューするなど
プレタポルテ部門参加ブランドはさらに増えた。
モデル的には日本のブランドのショーで活躍してきた山口小夜子が
海外デザイナーのショーにも引っ張りだこの状態となり、
1980年代半ばまでプレタポルテ部門の中心的モデルとして活躍。
また、富樫トコや秀香といった身長約180cmの大型日本人モデルも
1980年代を通じてモデルとしてパリコレで活躍。
ショーの注目度がスーパーモデルに注がれた1990年代前半
プレタポルテ部門の規模が年々大きくなっていく中、
各ブランドは有名なモデルをできるだけ多く起用して
マスコミや一般人からの注目度を高めようと考えるようになっていき、
そんな中で、
- シンディー・クロフォード(アメリカ)
- リンダ・エヴァンジェリスタ(カナダ)
- ナオミ・キャンペル(英国)
- クラウディア・シファー(ドイツ)
- クリスティー・ターリントン(アメリカ)
といったスーパーモデルが次々に誕生。
海外ではスーパーモデルに特化した情報雑誌なども創刊され、
1994年から1995年にかけては日本においても
"スーパーモデルブーム"が大きくクローズアップされる。
なお、その時期にカール・ラガーフェルドの目に留まった
日本人の川原亜矢子は当時のスーパーモデルブームの中、
数少ないアジア系スーパーモデルとしてシンディなどと共に大活躍していた。
スーパーモデルブームの崩壊
1995年あたりにピークを受けたスーパーモデルブームながら
1ステージ100万円前後まで高騰したと言われるトップモデルの
ギャラの高さが中規模メゾンの経営を圧迫するようになっていき、
1996年に入ると陰りが見え始めた。
1997年に入ると、ケイト・モスなどの新世代モデルは残った一方で
シンディーをはじめとした30代のモデルは次々にランウェイから姿を消し、
作品だけでなくモデルに過剰な注目が集める時代が終焉。
2000年代以降のパリコレ(多様性の時代が到来)
2000年代以降プレタポルテ部門の規模は拡大。
一方でオートクチュール部門はさらに規模・注目度が縮小していき、
オートクチュール部門から撤退するメゾンも急増。
しかし、一定の価値があるオートクチュール部門が消滅する事はなく、
流れとは逆にプレタポルテからオートクチュールへと転身する例もあり、
2010年代に入るとアントワープ王立芸術アカデミー卒業の
天才日本人デザイナー・中里唯馬がオートクチュール部門にデビューし、
長く活躍し続けている。
モデル面に関しては中国経済の発展を受け、
2000年代後半から中国からの注目度を高めるためにも
中国人モデルを起用しようとするブランドが増えていき、
そんな中から
- リウ・ウェン
- フェイフェイ・サン
といったスーパーモデルが誕生。
それを機にパリコレにおけるモデルの多様性は一気に明らかなものとなり、
2010年代に入ると中国以外のアジア系モデルや
アフリカ系モデルがランウェイに登場する確率も大幅に増加した。
メンズ部門は創設されてからオートクチュール部門同様に
規模・注目度が低い状況が続く中、
注目度の高いレディース(プレタポルテ)のショー内でメンズの作品も発表するという
男女混合形式のショーを開催する例が急増中。
関連ページ
一般的な用語(雑誌/トレンドetc)
ハイファッション系
人物/会社関連
業界誌系/業界用語
サイト内検索窓↓
(飛びたいページに即飛べます)
業界人必読(無料サンプル号あり)

Fujisan.co.jp:WWD JAPAN
[サイト内のファッション関連メニュー]