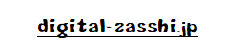服部金太郎(Kintaro Hattori)
参考文献
SEIKO会社公式サイト
服部真二 文化・スポーツ財団公式サイト
[https://museum.seiko.co.jp/]
公益財団法人服部報公会公式サイト
[http://www.hattori-hokokai.or.jp/]
| 生年月日 | 万延元年/1860年生まれ |
|---|---|
| 出身 | 江戸エリア/現在の東京都心 |
| 没年 | 昭和9年/1934年 |
| 異名 | 東洋の時計王 |
| 基本的な考え方 | 数歩先ではなく、消費者の一歩先行く経営/商売をする 急ぐな、休むな 精巧な時計を作る まず品質の高い商品を作り、安く売る事なく、やや高い価格設定をする |
| 主な功績 | 日本の時計業界のパイオニア 日本初の国産懐中時計・目覚まし時計・腕時計を製造 |
修業時代
江戸時代末期にあたる1860年、銀座付近の京橋エリアにて誕生。
13歳の頃から江戸時代から続く小林時計店で職人が働く姿をみる中で、
雨の日で客足が鈍る日でも修理の仕事で利益をあげられる仕組みに感嘆し、
時計業に強い興味をもつようになる。
そして、13歳の頃から日本橋の亀田時計店で修業を開始。
2年後には上野の坂田時計店に移籍し、時計の修理・販売ノウハウを学んだ。
なお、お世話になった坂田時計店は、
他の事業に失敗して倒産してしまって店主が困窮している中、
金太郎は店から去る際、恩人を救うために勤務時代の給料を返却した事が判明している。(彼の優れた人間性を表すエピソード)
1881年に事業を開始
修行生活を経て明治14年(1881年)、
時計の小売り・修理を行う「服部時計店」を生まれ育った京橋エリアで開業。
(これがSEIKOの歴史の原点)
1880年代半ばより横浜の外国人居留地とのビジネスをスタートし、
輸入腕時計の小売り事業で成功を収める。
外国人を相手にした時計の小売り事業で大きな資金を得たのち、
精工舎を1892年に設立し、まずは腕時計ではなく掛時計の製造をスタート。
なお、この精工舎という会社名には、「精巧な時計を作る」という大きな理念が込められている。
3年後の1895年には日本初の国産懐中時計のビジネスにも参入。
1899年には日本初の国産目覚まし時計の開発もスタートさせた。
20世紀(1900年代前半)
20世紀に突入してすぐの1901年には、会社の規模が国内時計業界のトップとなる。
この頃から海外事業もスタートして国際化がはじまる。
1911年時点では精工舎の時計が作品時計の6割のシェアを獲得するまでになった。
1913年には、かけ時計・懐中時計・目覚まし時計に続き、
ついに日本メーカーで初めて国産腕時計の製造を開始。
1923年には関東大震災で拠点全焼失の事態に見舞われたが、すぐに事業を再開。
1924年からは新ブランド「SEIKO」の商標を使い始める。
晩年の金太郎
晩年の1930年には私的財産300万円を投入して
公益事業援助などを目的とした「服部報公会」という財団法人を設立。
1933年、病に倒れたのち、
1934年(昭和9年)、73歳で死去。
死後、セイコー2代目社長の服部玄三(金太郎長男)も私財を投入して
「服部報公会」の規模をさらに大きくし、
湯川秀樹などサイエンス分野の偉人を表彰してきた。
関連人物
宝飾/腕時計関連メニュー
人物
会社(歴史/概要)